※この考察は本編4話の時点で書いています。本編とは異なる可能性が大いにありますが、大目に見てください。
名札の裏の3枚──
彼の人生を変えた、たった一つの記憶
設楽浩暉という男を読み解く鍵は、
彼が名札の裏に今でも大事にしまっている“3枚の紙”。
それは幼い頃、1人の少女──筒井万琴から受け取ったもの。
一見すれば微笑ましい思い出やけど、
浩暉にとってそれは「一生消えない何か」やった。
なぜ、たったそれだけのやり取りが今も心に残っているのか。
それは、あの日の記憶が“何かを救った記憶”やったからや。
可愛い子に貰ったからじゃない。
きっと、幼い頃の彼にとって、万琴の存在だけが唯一の救いやった。
20歳のあの日──
母の遺体、父の逮捕、そして「真実への確信」
浩暉が20歳の頃、母に呼び出されて訪れたアパート。
そこにあったのは──惨殺された母の遺体やった。
だが不可解なのは、浩暉の服に付いた血が“乾いていた”こと。
警察は最初、浩暉を疑う。
けど、なぜか逮捕されたのは父・貫路。
もしかすると浩暉は、犯人と直接遭遇していた。
あるいは、現場で“何かを目撃した”がゆえに、父が身代わりになったのかもしれない。
とにかく彼は、その日から「父ではなく、他に犯人がいる」と信じ続けた。
そして10年間、母の死の真相を追い続けた。
10年後の共謀──
劇場型犯罪が始まる
父・貫路が出所したのち、浩暉は記者としての立場を活かし、調査を続けていた。
母が企業の弁護士として、誰かに恨まれていた可能性。
そして、その背後に“殺意”を持った何者かの存在。
犯人はまだ社会にいて、自由に暮らしている。
そこで、貫路が提案する。
「炙り出すには、同じ地獄を見せるしかない」
浩暉は反対した。けど、父の決意は揺るがない。
止められないなら、自分も共犯になる──
浩暉はそう覚悟を決めた。
こうして「母の事件を思い出させ、真犯人に揺さぶりをかける」ための、
劇場型の連続模倣殺人が始まった。
万琴を傷つけたのは、守るためだった
万琴たちが“犯人の行動パターン”を予測し動き始めた日。
それは浩暉にとって、最も苦しい夜やった。
犯行対象はすでに決まっている。
父も動き出すつもりでいる。
警察の目は厳しく、誤算が起これば“本物の地獄”になる。
浩暉は決断する。
自分が犯人のフリをして、万琴を襲うことで
──貫路に“殺人の時間”を与える。
刃物は貫路が過去に使用したもの。
自分の痕跡で“上書き”する意図やった。
だが──
万琴は、本当に傷ついてしまった。
彼女を抱きしめながら、浩暉が何度も繰り返した「ごめん」は、
全方向への懺悔やった。
殺人を止めることができなかった男
浩暉は直接手を下していない。
けど、“止めなかった”時点で加担者や。
そして、何よりその事実を一番理解しているのが浩暉自身。
彼は誰かを守りたかった。
でも、誰も救えていない。
それでも、自分が壊れてでも守るしかなかった。
だからこそ、彼は何も言わずに立ち続ける。
誰にも説明せず、責められるまま受け止める。
最後に彼が選ぶのは、“伝える”こと
浩暉は記者や。
それは、彼が選んだ“語る者”としての生き方。
たとえそれが自分の罪を暴くことになったとしても、
彼は最終的に「真実を残す」側に立つと信じたい。
誰にも届かなくてもいい。
自分だけが知っていればいい。
それでも、“伝えようとした事実”は残る。
それが彼なりの、母への供養であり、
万琴への答えなんかもしれない。
結論:設楽浩暉という人間の本質
設楽浩暉は、
「優しすぎて、人を傷つける罪を抱えてしまった男」や。
誰よりも他人の痛みがわかるからこそ、
沈黙を選び、嘘をつき、壊れていくことを選んだ。
けどその奥には、
**本当に人を愛せる人間の“強さ”**が、ずっと眠ってる。
闇に生きる者こそ、
いちばん光を求めてるんや──この物語は、そう語っている。
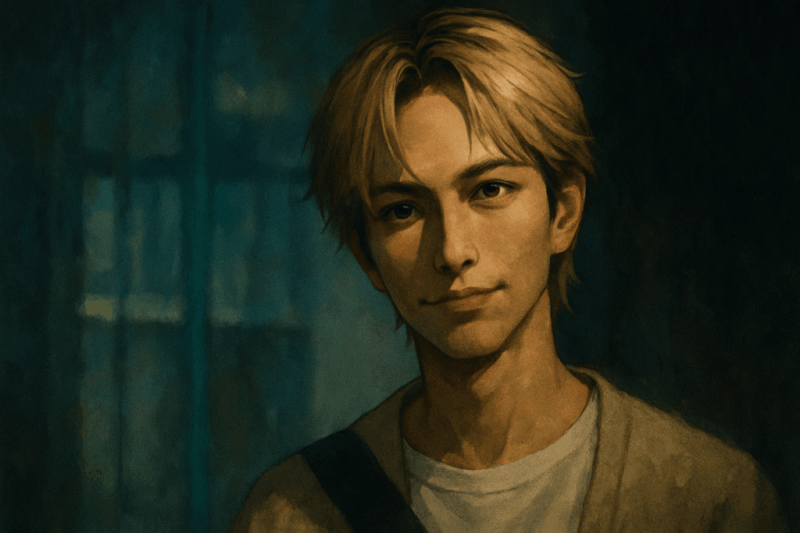
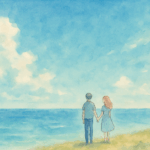




コメント